太陽電池研究者 櫻井啓一郎【メガ発インタビュー】

前回のインタビューではエネルギーアナリストである大場紀章氏に電力のP2P取引についてお話をお伺いしました。
今回は
『今後、太陽光発電はどのような不具合が想定される?』
『太陽光パネルのリサイクルは可能?』
『再エネ関連で盛り上がりを見せそうな市場は?』
などについて、産業技術総合研究所の主任研究員である櫻井啓一郎氏に話をお伺いしました。
櫻井啓一郎氏の研究内容とは

まずはじめに、太陽電池というのはご存知の通り発電するときに燃料がいらないんですよね。発電コストの大部分というのは設備を設置するときにかかります。 火力発電所であれば発電するときに燃料のコストが大きな部分を占めるのですが、太陽光発電のコストの大半は設備購入時にかかるんですね。
なので最初同じコストで設置したものが20年ではなく30年、40年というふうにもっとより長く使えればそれだけ発電コストは下がるわけです。そこで重要になるのが太陽電池のモジュールあるいは周辺機器の寿命です。これをいかに同じコストまたはそれよりも低いコストで寿命を長くするかという研究を行っています。
それで20年前〜30年前の市販品の太陽電池モジュールを実際に20年〜30年ほど屋外に設置してどれくらい出力が下がったかという報告が世界中にたくさんあるんですね。
そのデータを取りまとめて平均的にどれくらい寿命があるかというのを調べた研究があるんですよ。それによると20年後に出力が80%を切っているかという判断基準でみると、おおよそ2割の太陽光電池モジュールが20年持ちませんでした。5分の1の太陽光パネルが20年持たないのはマズいですよね。
それで8年前くらいからの話になりますが、太陽電池モジュールの耐久性を調べる試験規格があるんですけれども、それをいままとめてアップデートしています。世界中の研究機関と企業がノウハウを持ち寄って、こういうスキームであればこういうタイプの劣化を試験できましたなどといった情報交換を行っています。
またIECという世界の標準規格を定義している機関があるんですけれども、そこで太陽光に関連する規格をまとめて見直していて、今作業中のものだけで80個以上あります。
具体的にどのような規格内容になりますでしょうか。
一つ例を挙げますと、モジュールの型式認証というのがありまして、審査を通過しないとほとんどの国で売れませんよっていう規格があるのですが、それもつい最近アップデートされてものすごく厳しくなっています。
目下進められている規格の見直しがひと段落してそれが実際の製品に反映されるようになると、20年後に80%以上の出力を維持する製品の割合が、以前の8割から、9割、さらに95%以上、という風に上がっていくのではないかと期待しています。
あとは実際にやってみないとわからないところもあるのですが、我々としては太陽光パネル設置から30~40年後でも80%以上の出力を保つことを目標に研究しておりますので、恐らく今後市場に出回る太陽光パネルの寿命はどんどん伸びていくものと期待しております。
規格の見直しというのはいつ頃くらいに終わるといった目安はありますか?
やればやるほど新しいネタが入ってきてキリが無いんですが、最も主体になるような規格の見直しというのは7、8年かけてようやく峠を越えつつあるといった状況です。
規格の見直しには結構な年数がかかるのですね。
そうですね。単純に太陽光パネルを温めて高湿度にして1000時間から2000時間様子を見てっていう試験が多かったんですけど、今はさらにそれに電圧をかけたり塩水をかけたり力を加えたり紫外線当てたりと、色々なストレス要因を複合して試験するようにしています。なのでひと昔前よりもかなり厳しくなっています。
という事はいま検査を通過している製品というのはそれなりに信頼性が高くなっていると?
昔よりは信頼性は高くなっているはずですね。とまぁ、話は長くなりましたがこんな研究を行っております(笑)
今後、太陽光発電はどのような不具合が想定される?
2012年7月からFITが施行され太陽光発電は爆発的に普及しました。日本に設置されてある太陽光パネルにおいて、これからどのような故障、不具合が想定されるとお考えでしょうか。
昔は太陽電池というのはものすごく高価でした。1970年代に太陽電池の研究が本格化したのですが、その頃で言うと家1件分(3kW)の太陽電池の価格は1億円しました(笑)
1億円ですか!?
そうです。その太陽電池だけで家が何軒も買えた時期がありました。なので現在の太陽電池の価格は100分の1近くになっていますね。当時はそれだけ高価なものを設置するわけですから、風で設備が吹き飛ばされたりすると困るわけですよ。なので現場の施工店さんがしっかりとした架台を作って風に飛ばされないように丁寧に施工されていたわけですね。
それこそその架台を、メーカーさんが供給する架台では強度が足りないという事で工務店さんが設計をしてました。ところがFIT施行後はそれまでに計画されていた導入量よりも急激なペースで太陽光発電が普及し始めました。メガソーラーに限って言えば数十倍のペースだったんですね。そのおかげでメガ発さんは商売になっているんだと思いますが。(笑)
現場で何が起きるのかと言いますと、今まで手慣れてた人たちしかできなかったような施工や設計とかがいきなりパっと飛び込んできた素人さんがいっぱいやるようになっちゃったんですね。そうすると当然ちょっとした風で飛ばされるような設備とか、あるいは火事を引き起こすような設備ですとかたくさん施工・設計されてしまうわけですね。なので今後、そういったトラブルはさらに増えると思いますね。
なぜかというと太陽光発電システムというのは数百ボルトから千ボルト以上まで扱う高電圧の設備です。それを野ざらしの外で20年も30年も運用するというのは、それだけでノウハウの塊です。そのような設備は設置する段階でその後の運用実績が決まるところがあります。その設計ができていないと、一例をあげるとちゃんとケーブルを固定していないと風でゆらゆらして断線になりかねないですよね。そういう発電所がたくさんあるようなので、火災の原因や発電量の低下に繋がります。
なのでこのままだとマズいので、ひと目見て危険を察知できる発電所は通報して、お役所の方から発電所のオーナーへ改善命令を出すべきですね。
危険な発電所を放置しておくと二次災害になりかねないですよね。
そうです。周りに迷惑をかけるような設備は片っ端から通報して改善させないといけないと思います。あとは太陽光発電所のオーナーにとっても経営上の大きなリスクなんですよ。それを認識してもらう必要がありますね。
一度購入して稼働し始めてそのまま放っておけばいいやとお考えの方もいらっしゃると思いますが実際はそうじゃないんです。しっかりと定期的に点検して火災事故を起こさないようにしないといけないですよね。純粋に経営上から見て。そういう意識改革を発電所のオーナーに対してやっていくべきでしょうし、定期点検も義務付けるくらいのことをやった方がいいかもしれませんね。
そうですね。それこそ2017年4月に改正FIT法が施行されましたが、いま思うと数年前は低圧野立て太陽光発電所のフェンスの設置を義務付けていなかったの危険でしたよね。
こどもが設備内に侵入して感電するかもしれないですからね。最近世間で騒がれるようになってようやく改善される動きが出てきました。なので世間の関心が高いうちに制度を固めていっていただきたいなと思ってます。
あとつい最近ニュースになった屋根一体型太陽光発電の火災ですね。あれは我々も何年も前から危ないのではないかと言ってきたのですが、こういう商品はどんどんリコールさせるべきなのではないかと思っています。
また万が一の火災に備えた仕掛けを組み込むような方向に話をもっていってほしいなと思います。そういう対策・技術自体はあるので、ちょっとでも漏電が起こったときはパネル1枚毎に回路を遮断するといった技術もあります。
パネル1枚毎に回路を遮断する技術は確立されているのですね。
はい。パネル1枚毎に制御回路を付けて、配線経由で集中制御する事が可能です。なので例えばその通信が断たれたら断線が起こった可能性が高いというのでその時点でそのパネルの発電を止めることができます。それだけで安全性はかなり高まります。
すでにアメリカでは消防基準が改定されまして、この技術を使うよう義務付けられています。各州の法令とかに反映されていくに従ってだんだん普及していく形になるはずですけれども、基本的にアメリカではもう事実上そのような仕掛けが無いと売れない、という形になるはずです。
となると安全面の対策は日本よりアメリカの方が進んでいるのですか。
アメリカの方が進んでいます。日本は太陽光発電の普及と同時に安全面の対策も進めていかなければならなかったはずなんですが、2012年のFIT施行から改正FITが施行されるまでずっと止まったままだったんです。
ある程度しょうがないところもあったと思いますが、FITというのは施行してちょっと試してみて問題が起きたら直しながら進むところがあるんです。それを走りながら直していくというコンセプトでその当時、法律が制定されました。なので細かい部分は省令で直していく前提の設計になっていたんですね。FITはこれからも徐々に改善していかなければなりません。最低限安全性が保たれた上でコストが下がっていくようにしたいですね。
太陽光パネルのリサイクルは可能?

櫻井様のツイートにもありましたが、今後太陽光パネルの廃棄量は加速度的に増えると予想されています。太陽光パネルの寿命を迎えた場合、環境保全のためにリサイクルをする必要があるかと思いますが、現時点でパネルのリサイクルは現実的に可能でしょうか。
またリサイクルが可能な場合、コストはどのくらいかかりますでしょうか。
結論から申し上げますと太陽光パネルのリサイクルは可能です。というのもヨーロッパなどで既に先例があります。もう10年くらい稼働してますね。PV CYCLEというリサイクルシステムが動いているんです。
ヨーロッパは太陽光パネルのリサイクルを義務付けているんです。WEEE指令というものがあるんですけれども、そこで今の時点ですと85%以上の製品を回収するようにしないといけない形になっています。なのでリサイクル専用システムを使って回収できるように太陽光パネルのメーカーが資金を出し合っています。
あと技術的には日本ではリサイクルの実証事業というのは既に実施してまして、北九州にリサイクル工場がありましてトン単位で処理しているはずです。実際に実績として太陽光パネルの重量の95%をリサイクルできる材料に戻したという話も耳にしています。
このリサイクルされた材料をもとにまた太陽光パネルを作ることは可能ですか?
可能です。重量の割合を大きく占めているのはガラスとアルミフレームですから、今でも普通にリサイクルされていますよね。なのでまずは太陽光パネルを解体してそういう材料に戻せるという事です。あと配線の銅線ですね。
太陽電池そのもの(多くはシリコン製)のリサイクルも可能なんですが、現時点ではリサイクルできるパネルの量が少ないのでなかなか難しいかもしれません。今後太陽光パネルのリサイクルの量が増えてくればシリコン自体もリサイクルすることになるでしょう。
なので現時点ではガラス、アルミフレーム、配線の銅をリサイクルする形になります。
パネルには有害物質も含まれていますよね。
一般的な結晶シリコン型ではあまり使われていません。一部の製品でハンダ付けに鉛が使われているぐらいでしょうか。有害物質を含んでいるパネルもあります。例えばカドミウムテルル(テルル化カドミウム)の太陽光パネルは日本では製造していないのですが、ファーストソーラーという大手メーカーさんがこの物質を含んだパネルを製造しています。
しかし、ファーストソーラーさんは自社でリサイクルシステムを構築しています。パネルを解体してパネルに使っているカドミウムテルルも95%以上回収しているそうです。
リサイクルシステムが日本でもできていないとおかしいのですが、体制が遅れているので太陽光パネルのリサイクルは早く義務付けてほしいところですね。
太陽光パネルはどのように進化していく?
太陽光パネルは最近では370Wを超える高効率のモジュールが市場に出回っていますが、太陽光パネルは今後どのように進化していくとお考えでしょうか。
太陽光パネルにおいては生産の単価が安くなったので、使用用途が飛躍的に広がっているんです。例えば地域で言いますと太陽光パネルは日米欧の先進国でしか使われていなかったんですが、今ではアフリカ、中東、南米といった発展途上国でも使われていますし、あとは日射量が低かった北極地方の地域でも太陽光パネルが使われるようになっています。
このように地域的に広がりをみせているので例えばより暑い気候に対応する必要があるですとか、積雪や凍結でも破損しないモジュールが求められています。あとはふつうに屋根ですとか地面に置くだけではなくて、建物の一部として組み込むBIPVですとか、あるいは水の上に浮かべるものなど、昔は無かったところに取り付ける太陽光パネルが求められているので、将来的に色々な形でどんどん増えていくであろうと考えています。
太陽光パネルの出力数(W数)も今後さらに上がっていきますか?
上がっていくと思いますが、今のシリコンのままだと効率自体はそんなに上がっていかないことが予測されるので、タンデム化と言って他の材料の太陽電池と重ねて変換効率を上げるという技術は今後出てくるかもしれません。
いま研究中ですのでいつ世に出てくるかといったところですが、ひょっとしたら10年、20年後には今よりもずっと高効率の太陽光パネルが世に出回っているかもしれませんね。
再エネ関連で盛り上がりを見せそうな市場は?

櫻井様は太陽光モジュールや固定価格買取制度など様々な研究をされていますが、今後、再エネ関連のマーケットにおいて盛り上がりを見せそうな市場はありますでしょうか。
地域的に言うと先ほどもお伝えしたように発展途上国ですね。発展途上国でどのような使われ方をするかというと、まず電気が全くないところでディーゼル発電を使っているので、まず太陽光発電と蓄電池による置き換えが始まっています。
というのもディーゼルで発電するより太陽光発電と蓄電池を組み合わせて発電した方が安いんですよ。今までのディーゼル発電よりさらに安いコストで電力が手に入るようになった上、途上国の人たちが経済力を付けてきてインフラにお金を出せるようになったので、今まで電気が使われていなかったところに電力を届けることができるようになってきたんです。
当然その太陽電池を使った電力供給のシステムがまず売られるようになるんですけれども、太陽電池自体は安価なので大きな商売にはならないでしょう。その安価なものを使って電力供給のインフラを作る商売がすでに増えはじめています。太陽電池はあくまで商材の一つでしかありません。
それと合わせて蓄電池ですね。蓄電池もここ最近は安くなってきていますが。あと太陽電池だけでは電力供給しにくいよねってなってくると当然他の電源も一緒に買われますよね。例えば風車ですとかあるいは水力であったり、もっと規模が大きくなってくると地域でマイクログリッドをこさえて色々な電源や蓄電池を組み合わせて電気を供給するという商売も既に出てきています。これは先進国でも使われます。地域でマイクログリッドを構築した方が電力が安くできる事例がでてきたためです。
基本的にはマイクログリッドで地域内で電力を供給して足りないときだけ外部から供給する。ただ外部から供給する電力は値段は比較的高いです。(笑)なのでこのように太陽電池は商材の一つとして使って何かサービスを提供するという事が大事なのではないかと思います。
他に盛り上がりを見せそうな市場はありますか?
需要側の調整力の活用への組み込みですね。例えば今日の北海道の夜はすごく寒いから電力を多く消費することがありますよね。そういう時に家にある電気自動車から逆に系統に電気を戻すことができると、北海道の電力の需給がひっ迫しない可能性が高いですよね。太陽電池が発電している間はいいのですが、日が沈んでしまって各家庭でエアコンのスイッチをオンにしたり調理を始めたときに電力消費がピークになる時間帯があると思うのですが、ピーク時の電力供給が大変なんですね。
なのでそういったときに家にある電気自動車で余った電力を系統に戻すことができると電力会社としては楽ですよね。各家庭では数kWhにしかならないのですが、これが何百万軒と集まればものすごい調整力になるんですね。もう大規模発電所が何個もいらなくなるようなでかい調整力になります。そういった調整力を集めて電力市場に売る、そういったアグリゲーターのサービスが今後伸びてくるはずです。というか伸びてくれないと困ります(笑)そうしないとムダが出ます。
需要側の調整力の活用はヨーロッパやアメリカでは既に採用されていて、いままさに電力が足りないというときには各家庭の電力消費を抑えたり蓄電池から放電してもらったりといったことを瞬間的に全自動で行います。このシステムは他国では使われていて、日本は要素技術は持っているはずなのに実際のサービスを構築して売り物にまで仕立てるという部分で出遅れていますね。
あと蓄電池はものすごい勢いで伸張するとみられています。数年前までの価格の予測が全く役に立たないくらいのペースで値段が下がっています。オーストラリアですと電力系統に蓄電池を繋いで使う方が、ヘタに火力発電所を立てて調整力として使うよりも安くなっています。
例えば4時間分の蓄電池だったら真昼に太陽光で電力を溜めて夕方に使った方が、火力発電所で調整するよりも蓄電池で電力の需給バランスを調整した方が安くなっています。安くなると当然需要も増えるので今後ゆきだるま式に増えていくと思いますね。
少し話が変わってしまいますが、太陽光パネルの寿命は将来的に40年、50年と持たせる事はできますか。
そもそも長寿命の太陽光パネルが必要なのかという話もありますけどね(笑)市場がそこまで求めるかという話になってくるのですが、技術的にはいくらでも丈夫にする事は可能です。お金さえかければいくらでもできます。
なのでコストを下げつつ寿命を伸ばすというところで、引き続き研究が進められています。今日では25年間のパネル出力保証をしているメーカーさんが多いですよね?なので今後は30年、40年と伸びていくとは思います。ただ全てのメーカーがそうなるかというと、またそれは市場の要求次第かなという気はしてます。それこそビルの壁一体型の太陽光パネルなどは工事が大変なので長い寿命が求められますよね。壁一体型の太陽光パネルは弊所内にもありますよ。このようなものを建材一体型太陽光発電というのですが、ヨーロッパでは盛り上がってますね。
ヨーロッパの方たちはデザインにこだわりを持ってらっしゃいます。昔は太陽電池積んでますよーていうデザインの建物が多かったのですが、最近では注視しないとわからないような太陽光パネルの設置方法が求められてるみたいで、あんまり下から見ても見えないですとか、壁の模様に溶け込んでいてわからないようなパネルの需要というのも出てきてますね。それこそレンガ模様の太陽光パネルもあったりします。日本でどのくらい盛り上がりを見せるか個人的には興味を持っていますね。(笑)こうした建材一体型等の製品が牽引役になって、寿命が延びていくのかも知れません。
本日はありがとうございました。
プロフィール
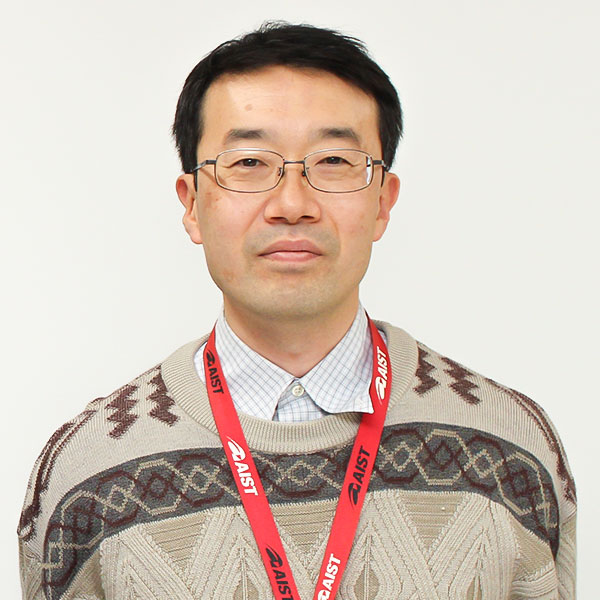
太陽電池研究者
櫻井啓一郎
学士:京都大学 工学部 第二電気工学科 長尾研究室
修士・博士:京都大学 工学研究科 電子工学専攻 光材料物性工学研究室
著書『トコトンやさしい太陽電池の本』『波に乗れ にっぽんの太陽電池』など
2008年11月より独立行政法人産業技術総合研究所に所属。太陽電池の耐久性や信頼性を上げ、再生可能エネルギーの普及対策に力を入れている。
Twitter:@kei_sakurai
インタビューを終えて
太陽電池研究者の櫻井啓一郎氏にお話をお伺いしてみて、太陽光パネルの性能はこれからもぐんぐん上がっていくとの事なので、今後の新製品には要注目ですね。また、1970年代の太陽光パネルの導入費用は家1件分(3kW)で1億円と、今の導入費用の約100倍なので驚きでした。
太陽光パネルのリサイクルにおいては欧州のPV CYCLEのようなリサイクルシステムを日本でも構築できれば安心ですね。今後、日本のPVリサイクル市場の動向に注目していこうと思います。
メガ発では引き続き太陽光発電所の販売店やエネルギー関連の従事者に取材して参ります!

 ポスト
ポスト

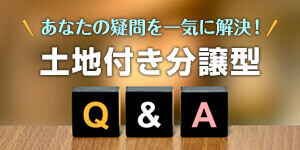













産業技術総合研究所に在籍されている櫻井さんですが、いま現在どのような研究をされていますか。