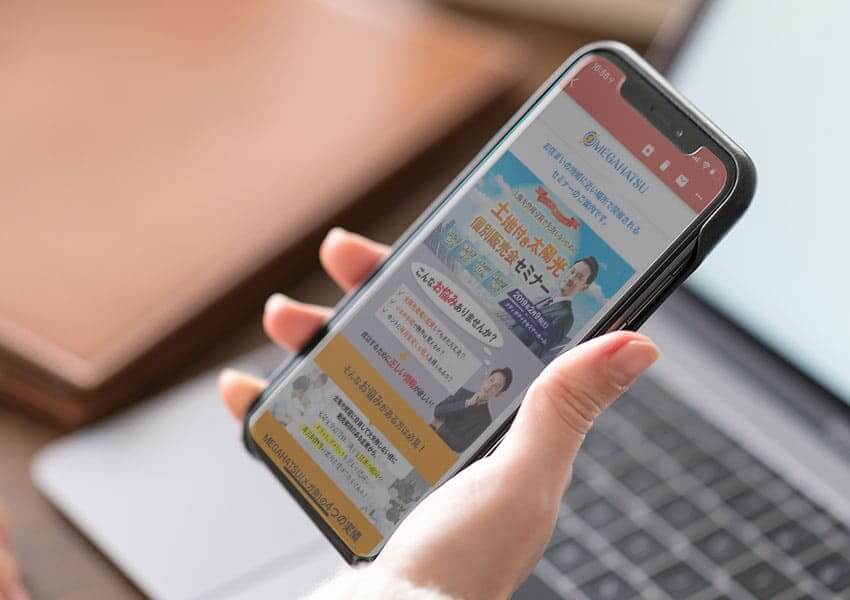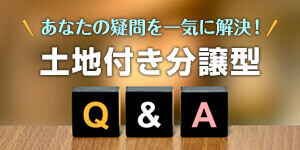FIP制度とは?FIT制度との違いやメリットをわかりやすく解説
公開日:2025/11/23 | | カテゴリ:太陽光発電投資の基礎知識
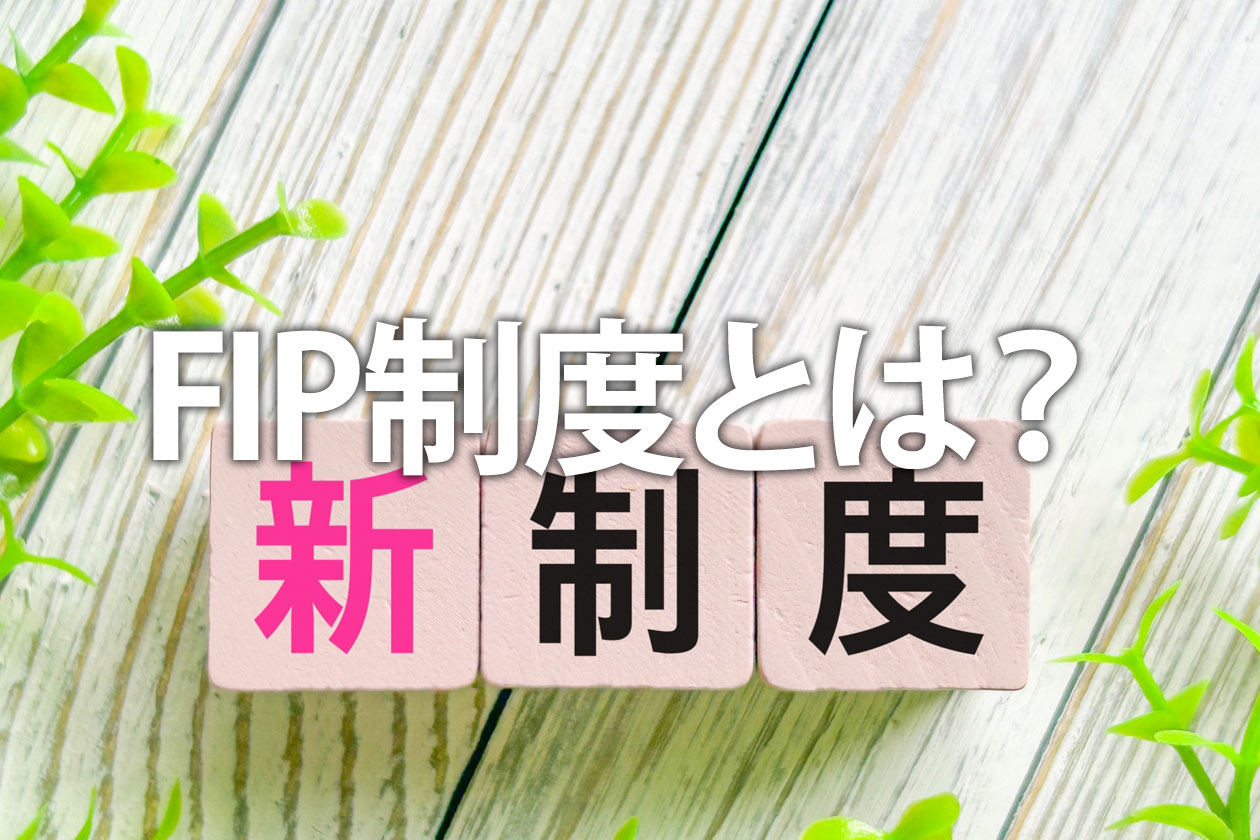
FIP制度は、再生可能エネルギーの導入を促進するための新しい電力買取制度です。
従来のFIT制度が固定価格での買取を保証するのに対し、FIP制度では市場価格に補助額を上乗せする形で収益が決まります。
この記事では、両制度の違いやFIP制度の仕組み、事業者にとってのメリット・デメリットをわかりやすく解説します。
目次
FIP制度とは?再エネを電力市場へ統合する新しい売電の仕組み
FIP制度とは「Feed-inPremium」の略称で、再生可能エネルギー発電事業者が卸電力市場や相対取引などを通じて自ら電力を売電し、その売電価格に加えて一定の補助額(プレミアム)を受け取れる制度です。
従来の固定価格買取制度(FIT制度)が、再エネの導入量を増やすことを主目的としていたのに対し、FIP制度は再エネを電力市場に統合し、自立した電源とすることを目的としています。
どこが違う?FIP制度とFIT制度の3つのポイントを比較
FIP制度と従来のfit制度は、再生可能エネルギーの買取方法において根本的な違いがあります。
具体的には、売電価格の決定方法、需給管理責任の所在、そして環境価値の扱いの3点が大きく異なります。
これらの違いを理解することが、事業計画を立てる上で重要になります。
売電価格の決まり方:市場価格に連動するか固定か
FIT制度では、国が定めた固定価格で一定期間、電力会社が買い取ることが義務付けられています。
一方、FIP制度では、発電事業者は卸電力市場や相対取引で自ら電力を販売し、収入は市場価格に応じて変動します。
この市場での売電収入に加え、プレミアムと呼ばれる補助額が交付される仕組みです。
そのため、発電事業者は入札のタイミングを工夫するなど、市場価格を意識した事業運営が求められます。
固定価格で安定収入が見込めるFIT制度と異なり、FIP制度は事業者の創意工夫によって収益を最大化できる可能性があります。
発電量の需給管理責任(インバランス)は誰が負うのか
FIT制度では、発電計画と実績の差(インバランス)から生じるコストは、電力を買い取る電力会社が負担します。
これに対し、FIP制度では発電事業者が自ら需給管理の責任を負う点が大きな特徴です。
計画値と実績値にズレが生じた場合、インバランス料金と呼ばれるペナルティが発生し、事業者の負担となります。
そのため、FIP制度を活用する事業者は、ITシステムなどを活用した精度の高い発電量予測や、計画通りの発電を行うための運用管理が不可欠です。
この需給管理業務を専門のアグリゲーターに委託するという選択肢も考えられます。
環境価値(非化石価値)の取り扱い方法
FIT制度では、太陽光発電などで作られた電気の環境価値は、電力の買い手である電力会社に帰属し、非化石価値取引市場で取引されます。
そのため、発電事業者が環境価値から直接収益を得ることはできませんでした。
一方、FIP制度では、発電した電力の環境価値は発電事業者に帰属します。
事業者は、非化石価値取引市場で証書として直接販売することが可能になり、売電収入に加えて新たな収益源を確保できる可能性があります。
これにより、環境への貢献度を企業価値としてアピールしやすくなる側面もあります。
FIP制度の収入はどう決まる?「プレミアム」の計算方法
FIP制度における発電事業者の総収入は、市場での売電収入と国から交付されるプレミアム(補助額)の合計で決まります。
このプレミアムは、事業者が安定して収益を確保できるよう設計されており、FIP価格、参照価格、バランシングコストという3つの要素から算出されます。
ここでは、その具体的な計算方法を解説します。
補助額の基準となる「FIP価格」
FIP価格は、再生可能エネルギー発電事業者が効率的な経営を行った場合に通常必要となる費用を基に設定される基準価格です。
この価格は、FIT制度における買取価格と同様に、電源の種類や規模に応じて、調達価格等算定委員会の意見を聴取した上で国が決定します。
FIP価格は、事業者が投資回収を見込むための重要な指標となり、プレミアム単価を算出する際の基礎となります。
この制度では、FIP価格から後述する参照価格を差し引いた金額がプレミアムの基本となるため、事業者は自社の発電コストがFIP価格に見合うものかを慎重に検討する必要があります。
市場の取引価格を反映する「参照価格」
参照価格は、市場で取引される電力価格の平均値に連動して変動する価格です。
具体的には、卸電力市場のスポット市場価格に、時間帯やエリアごとの係数を乗じて算出されます。
この参照価格は、発電事業者が市場から得るであろう平均的な収入を示す指標として機能します。
プレミアム単価は、FIP価格からこの参照価格を引いて計算されるため、市場価格が上昇して参照価格が高くなるとプレミアム単価は下がり、逆に市場価格が下落して参照価格が低くなるとプレミアム単価は上がります。
このように、市場価格の変動による収入の振れ幅を一定程度緩和する役割を担っています。
発電計画と実績の差を補う「バランシングコスト」
バランシングコストは、発電事業者が負う需給管理責任に伴う費用を指します。
FIP制度では、発電計画と実績の差を埋めるための費用を国が一部補助する考え方から、プレミアムの計算にこのコストが考慮されます。
具体的には、過去のインバランス料金の実績などから、1kWhあたりのバランシングコストが算定され、プレミアムに上乗せされます。
例えば太陽光発電では当初1kWhあたり1.0円と設定されました。
このコストは、非常に細かい市場データに基づいて算出されるため、例えば0.01円単位の変動が収益に影響を与える可能性もあります。
事業者は、このバランシングコストの考え方を理解し、インバランスを抑制する運用が求められます。
発電事業者がFIP制度を導入するメリット
FIP制度は、発電事業者にとって新たな責任やリスクを伴いますが、同時に大きなビジネスチャンスももたらします。
市場価格と連動することで収益を最大化できる可能性や、アグリゲーターとの連携による新事業の創出、さらには環境価値を直接収益化できる点などが主なメリットとして挙げられます。
これらを活用することで、事業の競争力を高めることが可能です。
電力市場の価格が高い時に売電収益を最大化できる
FIP制度のメリットは、電力の需要が高まり市場価格が上昇した際に、売電収入を大きく伸ばせる可能性がある点です。
固定価格で買い取られるFIT制度とは異なり、FIP制度では卸電力市場の価格に連動して収入が変動します。
そのため、蓄電池などを活用して、電力価格が高い時間帯を狙って売電するといった戦略的な運用が可能になります。
例えば、夏の昼間や冬の夕方など、電力需要がピークに達するタイミングで集中的に供給することで、プレミアムに頼らない収益の柱を築くこともできます。
市場の動向を的確に捉え、能動的に動くことで収益機会を拡大できます。
アグリゲーターとの連携など新たな事業機会が生まれる
FIP制度では、発電事業者が需給管理責任を負うため、発電量予測や市場取引といった専門的なノウハウが必要となります。
こうした業務負担を軽減し、効率的な運用を実現するために、アグリゲーターとの連携が新たな事業機会を生み出します。
アグリゲーターは、複数の発電所を束ねてIT技術を駆使し、高度な発電予測や最適な市場取引を代行する事業者です。
専門事業者に業務を委託することで、発電事業者はインバランスリスクを低減し、安定した収益確保を目指せます。
また、アグリゲーターが提供する多様なサービスを活用することで、自社のリソースを発電所の保守管理など、より中核的な業務に集中させられます。
非化石価値を直接市場で販売して収益化できる
FIT制度では発電事業者に帰属しなかった環境価値がFIP制度では事業者のものとなります。
これにより、発電事業者は「非化石価値取引市場」を通じて環境価値を証書として直接販売し、売電収入とは別の収益源を確保できます。
再生可能エネルギー由来の電力を求める企業や団体にとって、この非化石証書はRE100達成などの目標に貢献する価値を持ちます。
そのため、環境意識の高い需要家との間で直接取引を行うことも可能となり、新たなビジネスモデルの構築につながります。
自社の電気が持つ環境的な価値を収益に結びつけられる点は、FIP制度の大きなメリットの一つです。
FIP制度の導入前に知っておきたいデメリットと課題
FIP制度は多くのメリットがある一方で、発電事業者にとっては新たなリスクや課題も存在します。
特に、市場価格の変動による収入の不安定化、発電量予測の精度に伴う追加費用の発生、そして市場取引や需給管理といった運用面の負担増が挙げられます。
この制度へ移行する前には、これらのデメリットを十分に理解し、対策を検討しておくことが事業の成否を左右します。
市場価格の変動によって毎月の収入が不安定になるリスク
FIP制度における収入は、市場での売電収入とプレミアムで構成されますが、その根幹となる卸電力市場の価格は常に変動します。
燃料価格の高騰や需給バランスの変化など、様々な要因で電力価格は大きく上下するため、毎月の売電収入が不安定になるリスクを伴います。
FIT制度のような固定価格による安定した収入が見込めなくなるため、事業者はキャッシュフローの管理にこれまで以上の注意を払う必要があります。
特に、市場価格が低迷する時期には、プレミアムによる補助があっても収益が想定を下回る可能性があります。
長期的な事業計画を立てる際には、この価格変動リスクを織り込んだ収支シミュレーションが不可欠です。
正確な発電量予測ができなければ追加費用が発生する
FIP制度では、発電事業者が計画値同時同量の達成、つまり発電量の需給管理責任を負います。
特に天候に左右されやすい太陽光発電などでは、30分単位で提出する発電計画と実際の発電量に差異(インバランス)が生じやすくなります。
計画よりも発電量が少なかったり、逆に多すぎたりした場合、その差分を埋めるためのペナルティとしてインバランス料金が課されます。
この料金は発電事業者の直接的なコスト増につながるため、収益を圧迫する要因となります。
精度の高い発電量予測システムの導入や、気象情報を活用した緻密な運用管理ができない場合、予期せぬ追加費用が発生するリスクを常に抱えることになります。
電力市場での取引や需給管理など運用負担が増加する
これまでのfit制度では、発電した電気を電力会社に供給するだけでよかったため、事業者の運用負担は比較的軽いものでした。
しかし、FIP制度では、発電事業者自らが卸電力市場での入札や相対取引を行い、買い手を見つける必要があります。
さらに、30分単位での発電計画の策定と提出、インバランスの管理といった需給管理業務も発生します。
これらの業務には、市場動向の分析や価格予測、計画策定といった専門的な知識とスキルが求められ、事業者側の運用体制を大幅に強化しなければなりません。
こうした新たな業務への対応が、人的・時間的コストの増加につながる点は、FIP制度へ移行する上での大きな課題です。
まとめ
FIP制度略してFIPは再生可能エネルギーの自立を促し電力市場への統合を目指す制度です
固定価格で買い取られるFIT制度とは異なり市場価格に連動した収入とプレミアムから構成されるため事業者の市場対応力が収益を左右します
メリットとして市場価格高騰時の収益最大化や環境価値の直接販売が挙げられる一方収入の不安定化や需給管理責任といったデメリットも存在します
事業者にとってはこれらの特性を理解しアグリゲーターの活用なども含めた事業戦略を構築することが求められます

 ポスト
ポスト